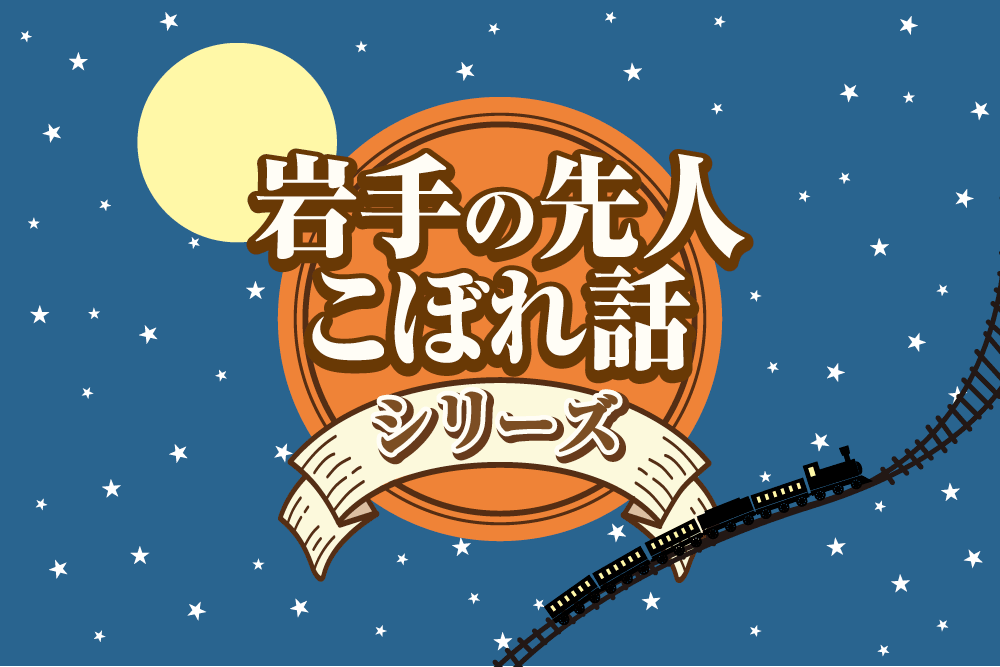徳川幕府が諸大名を統制する手段の一つとして実施されたのがお預け(流刑)です。江戸時代を通じて24人が盛岡にお預けとなりましたが、代表的な人物が栗山大膳(くりやまだいぜん)です。
大膳は家老として黒田藩(福岡藩)主・黒田長政に仕え、長政亡き後は嗣子(しし)・忠之を支えましたが、忠之は酒色におぼれ藩政をおろそかにするようになりました。大膳は忠之を諫めましたが、逆に怒りを買い、生命と家禄が没収される危機に陥りました。
智略に優れていた大膳は1632(寛永9)年、「忠之に謀反の疑いがある」と幕府に訴えました。幕府は訴えを吟味し、忠之を謹慎処分とし、大膳を盛岡藩にお預けとしたのです(黒田騒動)。大膳は翌1633(寛永10)年、盛岡に移送されました。
時の盛岡藩主・南部重直は大膳に広大な屋敷を与えるなどして、厚くもてなしました。そして1652(慶安5)年、62歳で亡くなるまで、大膳は盛岡で不自由なく暮らしました。お預け人であったため、子孫は母の姓である「内山」氏を名乗り、明治維新を迎えるまで南部家に仕えました。大膳の生涯に関しては、森鴎外が歴史小説「栗山大膳」を執筆しています。