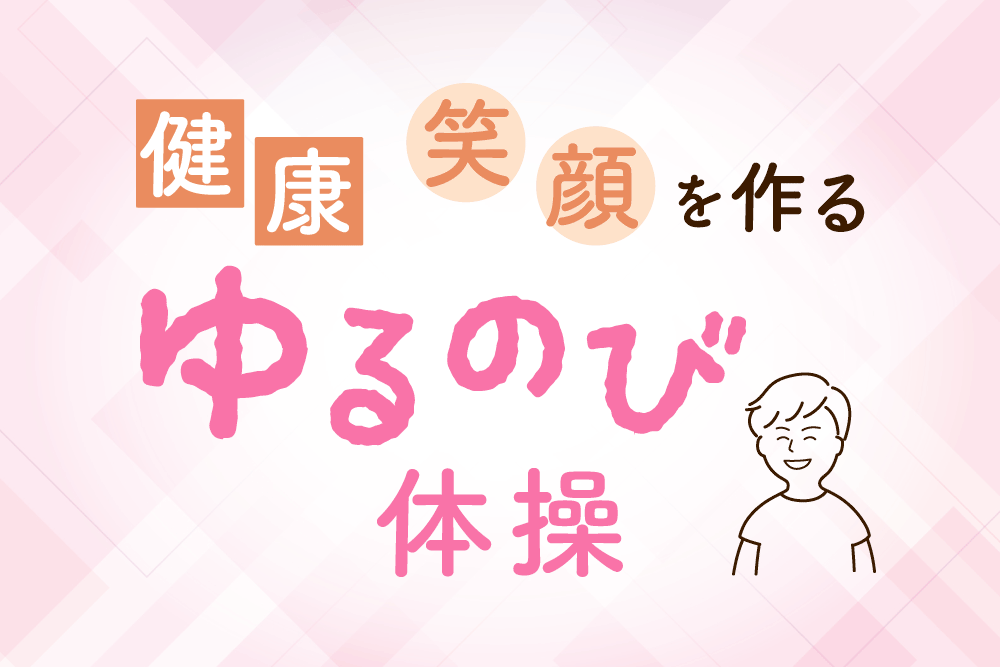寒さや積雪が厳しい岩手では暖房器具は欠かせない存在です。しかし、気になるのが空気の乾燥。本日は皆さんが一度は経験したことがある乾燥肌についてお話しいたします。
皮膚が乾燥している状態を皮膚科の専門用語では、「乾皮症」あるいは「皮脂欠乏症」といいます。皮膚の水分が減少し、うるおいがなく、乾燥してカサカサした状態です。皮膚の状態としては、鱗屑(かさかさ)が付き、時に亀裂(ひびわれ)がみられます。皮膚がざらざらしたり、ブツブツしたりするサメ肌のようになることもあります。
乾燥した皮膚は刺激を受けやすくなります。正常な状態の皮膚では痒くならないような軽い刺激、例えば服でこすれる、あるいは少し温まるというだけでも痒くなります。痒くなると掻いてしまい、その結果、乾燥に加えて湿疹ができます。これを「皮脂欠乏性湿疹」といいます。
さて、乾皮症(皮脂欠乏症)は、中高齢者に多い傾向にあります。下腿伸側(足のすね)、腰背部(腰まわり)に生じることが多く、外気が乾燥し、発汗量が低下する秋~冬にかけて症状が出現します。
乾皮症になる原因(理由)として、水分を保つ機能が落ち、皮膚の水分量が少なくなることがあげられます。そうなる原因としては3つあります。1つ目が加齢です。年齢を重ねるにつれて、水分を保持する力が低下し、肌が乾燥しやすくなります。2つ目として環境要因、すなわち湿度が低くなる環境があります。暖房などを使用し、空気が乾燥した環境に長時間いたり、入浴時の脱脂力の強い洗浄料の使用やナイロンタオルなどによるこすり洗い、高温のお湯への入浴なども皮膚の水分保持機能を低下させる原因として考えられています。そして、3つ目は湿疹などの皮膚疾患や全身疾患に伴うもの、あるいは抗がん剤の治療や放射線治療などを受けているときに症状が出ることがあります。
今回はしばしば生じる「乾皮症」について説明しました。
皮膚に関して気になる症状があるときは皮膚科の専門医にご相談ください。
岩手医科大学医学部
皮膚科学講座
天野 博雄
■取材協力