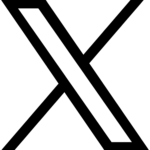命つき果てるまで推敲(すいこう)を重ね、ついに決定稿に至らなかった(つまり未完成のままの)『銀河鉄道の夜』。この作品で宮沢賢治は一体何を語ろうとしたのか。
夢うつつの中、銀河鉄道で旅するというジョバンニとカムパネルラの物語は、自分を虐めていた友人を助けるためカムパネルラが溺死したという不条理が最後に浮かび上がり、幻想旅の答えとなって終わる。死生観とそこに潜むジレンマが物語のテーマであると読後わかってくるのだ。
そもそも賢治は、死というものへの考え方を、自身の信仰の変遷とともに深めており、最愛の妹トシの死や、自ら病のため死と隣り合わせにいることに揺れながら、常に死を想い、死を忘れてはいけないという自己警鐘や畏れめいたものを(ラテン語の「メメント・モリ」ではないが)作品に投影して来たのではないのかとさえ思える。
銀河を旅するジョバンニとカムパネルラ。2人の前には不思議な出会いと別れが連続するが、その中で濡れた髪をした男の子、青年、女の子の3人が現れるくだりがある。乗っていた船が氷山にぶつかり、救命ボートを人に譲った後、気づくとここにいたと彼らは語る。まさに1912(明治45)年に起きたタイタニック号の事故を彷彿(ほうふつ)とさせる逸話だ。
人はいきなり死と隣り合わせとなった時、誰もが本性のままに行動してしまう。タイタニック事件など、その最たるものだっただろう。
女性と子どもを優先させていた救命ボートを取り巻いて、本性のせめぎ合いがあった。理性を失った人間は躊躇(ちゅうちょ)なく他人を蹴落としたりもする。自分を犠牲にしても人を助けるか、自分の命を優先するか。ジレンマに苛(さいな)まれながら短時間で己の行動を選ばなければならない時、どう決断するかなど、平和な時に考えても意味がないのかもしれない。修羅場に直面した非常時、どう動くかは「神に誓って」とまでは正直私は言いきれない。きっと誰もがそうだろう。
この事故が起きた時、賢治は15歳だった。多感な少年も、この強烈な事件で死ぬこと、生きること、死して人を生かすこと、そうしたことのジレンマを悶々と思うようになったのだろうか。そう考え、そして自分も「人を生かすためなら死を選びたい」との理想を描き、挿話したのかもしれない。
死に直面する出来事はタイタニックだけではなく、賢治の生きた時代には日照りや冷夏による大飢饉、大地震や大津波などの災害も日常にあった。なにしろ賢治が生まれた年(明治29年)に明治三陸地震と大津波が発災している。もはや宿命的と言っていいだろう。
そんな賢治が東日本大震災の大津波や、世界中のコロナパンデミック、そして先頃の潜水艇タイタン号爆縮事件を知ったら、いったいどんなメッセージを発し、どんな形で世に問うたことだろう。