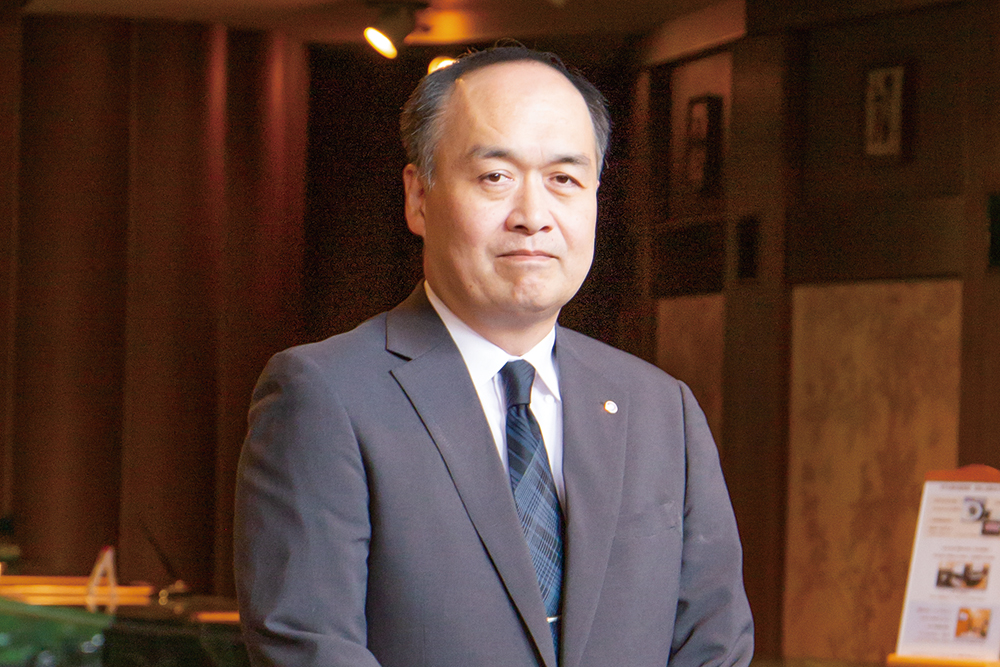● 震災を経験したから 気付いた地元の魅力
青森県八戸市から福島県相馬市まで続く、全長1000kmを超える「みちのく潮風トレイル」。三陸復興国立公園をはじめ東北沿岸の豊かな自然の中を歩きながら歴史や文化に触れ、地域の人々と交流し、震災からの再生を体感できる「ナショナルトレイル」として2019年に全線開通しました。「世界中にさまざまなトレイルコースがありますが、これほど海岸沿いを歩くことのできるコースはここだけです」と浄土ヶ浜ビジターセンター事務局長の佐々木洋介さん。岩泉町・宮古市・山田町にまたがる宮古市エリアのルート選定から維持管理まで行い、国内外から訪れるハイカーにトレイルの魅力を伝えています。
佐々木さんがトレイルに関わるきっかけとなったのは東日本大震災。「勤めていた会社も町も津波で壊れ、今まで目の前にあって当たり前だった景色の素晴らしさや地元への愛着に改めて気付かされました」。壊れた道路や建物はいずれ元に戻り、町が復興すればまた人が足を運んでくれるだろうと考えた佐々木さんは、生まれ育った宮古市で何かを「伝える」仕事に挑戦したいと被災から2カ月後に浄土ヶ浜ビジターセンターに転職しました。
●地元の皆さんと 一緒に作った道
東日本大震災の体験者として、観光客や小中学生に自然の脅威や恵みについて「伝える」日々を送っていた佐々木さん。2012年、環境省の「グリーン復興プロジェクト」の一環として「みちのく潮風トレイル」のルート選定がスタートし、環境省から東北沿岸の各ビジターセンターに協力依頼が。もちろん浄土ヶ浜ビジターセンターにも話が舞い込み、佐々木さんも宮古市エリアのトレイル作りのメンバーに加わることになりました。「がれきの撤去も終わっていないのに歩いて楽しむ道を作る。何か真逆なことをやっているような違和感がありました」と、当時の複雑な心境を振り返ります。それでも環境省職員や関係者と一緒に地域の公民館を回り、トレイルの説明に奔走。「ありのままの自然が見られる道をつなげて、最終的には1000kmの自然歩道を作りたいと地域の皆さんに協力をお願いして回りました。すると地元の高齢者の方が、地図に載っていない道を教えてくれるんです」と佐々木さん。実際に現地に足を運ぶと、草が生い茂ってはいるものの確かに歩いた痕跡があり、地元の方が子どもの頃に遊んだ裏山の道、学校へ続く裏道などがトレイルコースに採用されました。「私が部活で走っていた道もコースに含まれています」と笑顔の佐々木さん。地域住民を巻き込んだ道作りは「みちのく潮風トレイル」全エリアで行われ、各地域ごとに特色あるコース作りが行われました。「地元の人でなければ知らないルートもあり、より地域の暮らしや文化を感じられるコースになっています。当初は疑問もありましたが、地元の方と一緒に道を作り歩き、今はやって正解だったと思っています」と話します。
トレイル作りのやりがいをお聞きすると「自分の背丈を超えるような草むらから始まって、草を刈って道をつなげ、伸びたらまた刈ってと繰り返しているうちに、だんだん草が生えなくなって道になります。誰かが歩いてくれているんだなと実感できて嬉しいです」と佐々木さん。全く経験のない世界で正解が分からず悩むこともありますが、環境省をはじめコンセプトを持ちトレイルを作っている方たちと一緒に仕事をすることで学ぶことも多かったといいます。「岩手山もそうですが一般的に登山道は歩きやすく整備されていますが、トレイルはありのままの自然を残すために維持管理は必要最低限にします。仮に倒木があっても簡単にまたげるならそのまま自然に朽ち果てるのを待ちます。ただ、道の崩壊など危険があれば修繕し、ルートの変更も考えます」と佐々木さん。まだ正解にはたどり着いていませんが、道を歩いた人に感想を聞き、これからもより良いトレイルを提供していきたいと話します。
「トレイルの参加者は60代から80代の方が多いですよ」と佐々木さん。宮古市エリアは降雪量が少なく、真冬でも歩くことができると登山感覚で訪れるハイカーも増えているとか。「例年、ゴールデンウイーク前に浄土ヶ浜の山桜が見頃となり、その後は新緑が楽しめるので、これからの季節はトレイルに最適です」とのこと。スタートもゴールも、コースの難易度も自由に決められるトレイル。波の音を聞きながら、美しい海岸線を歩いてみませんか。