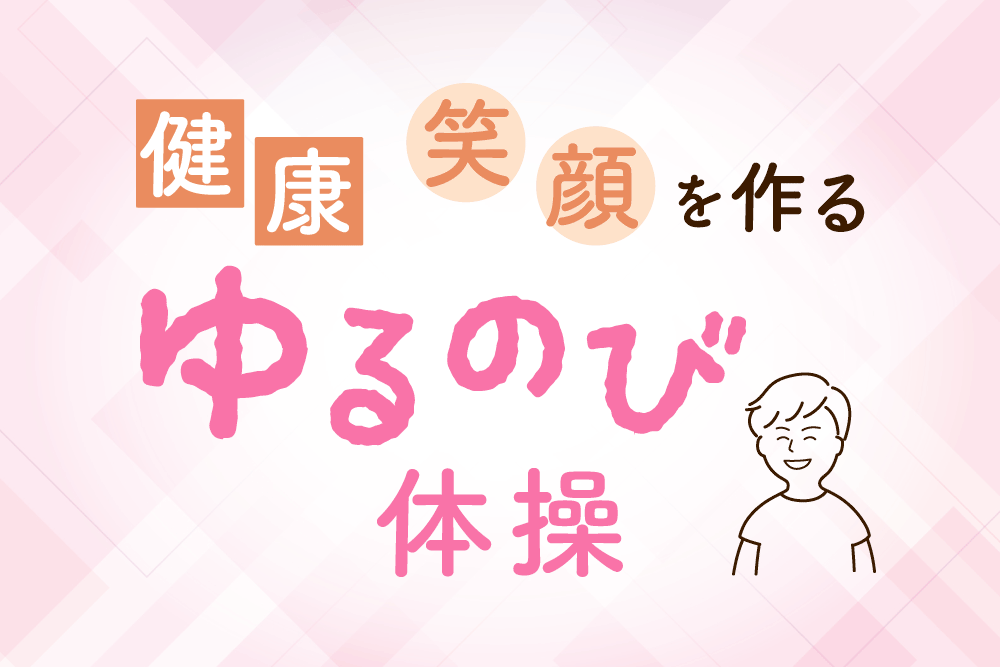【モニタリング①】
立って足裏のどこに強く体重がかかっているか確認しましょう。
【やり方】

指分け
座った状態で脚を伸ばします。ももの上に反対側の足をのせます。
ももにのせた足の親指を持ち、反対の手で人差し指を持ちます。両方の指が交互になるよう、付け根から縦方向に伸ばします。隣の指へと移り全ての指の間を広げるように動かします。指を伸ばした状態で分けましょう。

足首まわし
足の指と手の指を組み、付け根がしっかりとかみ合うように挟みます。
反対の手で足首をおさえ、つま先で大きな丸を描くようにゆっくりと足首を回します。
反対方向にも回します。
【モニタリング②】
運動前と足裏の感覚を比べてみましょう。足の裏が床にピッタリとついている感じがします。
【運動の効果】
転びにくくなる。
足がつることの予防。
冷えの改善。
テレビを見ながら、湯船に浸かっている時などに行いましょう。
※日本コンディショニング協会のメソッドを使用しています。