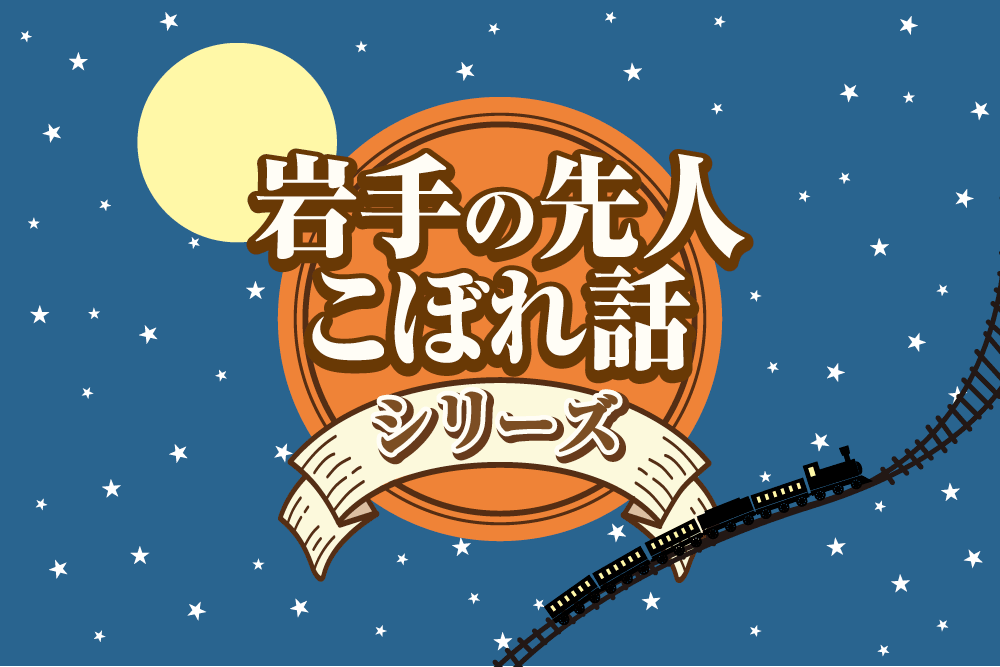東日本大震災後、ずっと気になっていることがある。三陸沿岸に点在する義経北行伝説ゆかりの神社の被災状況だ。震災のなか、古びた小さなお社たちは果たして無事だったのだろうか。だが現地に足を運び、安否を確認することができないまま今に至る。神社は集落の高台に祀られており、安全そうに感じるものだが、海辺から山間に細く延びる室浜集落の山裾に建つ釜石市片岸町の「法冠神社」や、宮古湾最奥部の津軽石地区の「判官神社」は、あの巨大津波になら簡単に飲み込まれてしまいそうなほど脆弱(ぜいじゃく)だ。暗澹(あんたん)たる思いのまま、あの日から間もなく11年が経つ。
このような未曾有の出来事を目のあたりにして、伝承というものは実にはかないものなのだなと強く感じる。平穏な環境や状況のなかでこそ、ゆかりの土地や物品は健全に保たれ、伝説は生き続けるのだ。むしろ当たり前こそが実は奇跡的なことなのかもしれない。
さて昨年九月に、このコラムをまとめて『岩手謎学漂流記』を上梓(じょうし)した。本のカバー用に著者近影の画像が一枚必要といわれ、私は北上山地の奥深くにある義経北行伝説ゆかりの神社を訪ねた。せっかくなので伝説地で写真を撮りたいと思ったのである。あえて地名や呼称は伏せるが、そこは古い氏族の氏神様なので撮影させてもらうため、私は写真家とともにまずその家を訪ねた。私有地とおぼしき神社がある裏山への入山と参拝の許可を得る必要があったのだ。対応に出て来たのは老齢のご婦人だった。以前も取材させてもらったことがあると伝えると「今ではこの家に暮らすのは自分一人で、足腰も悪いので神社の維持管理ができていない」と言う。確かに、かつて取材させていただいた時にはご主人も健在で、さまざまな興味深い口碑伝承を聞かせていただいたのだ。それでもぜひにとお願いを続けると「参道の草刈りもできていないので難儀だと思いますがどうぞ」と許可を得ることができた。
それから30分ほどかけて神社の鳥居に辿り着いた私たちはお賽銭をあげ、社殿内に祀られている神様に義経公を重ねながら手を合わせ、写真を撮影してもらって下山した。私は坂を下りながら、ふと一つの記憶をよみがえらせていた。それは震災前だった気がするが、辺りが青く染まった夕刻のことであった。たまたまこの近くを車で通りがかった時、この山腹に淡い橙色の光の群れが揺れているのを見たのである。おそらくあれは九十九折りの参道に沿って吊るされた無数の提灯(ちょうちん)だったのだろう。集落を上げて行われていた神社の祀礼の夜だったに違いない。
その土地の縁起にも関わる神社を守るのは、氏神を祀る一族や個人だけではない。その集落の住民や伝承を愛する多くの人たちも一丸となって守るからこそ「奇跡の存在」となりえる。守り人の老齢化で風前のともしびとなっている、この伝説地の継承活動に何か協力できることはないものだろうか。私は強く思っていた。