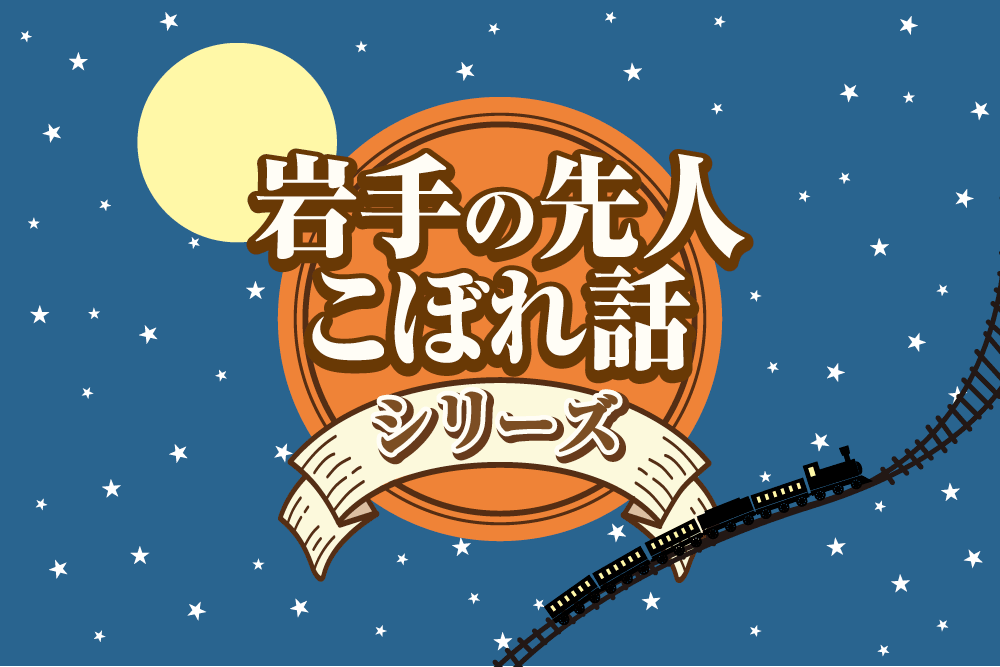宮古や山田にかなりな数の義経北行伝説地があるというのに、どうして岩泉には伝説の気配が希薄なのか。さらに北の久慈、八戸にも伝説が多い。岩泉だけが空白地帯というのは腑に落ちない。宮古あたりから海路で北へと進んだというのか。いや、その時代、小さめの舟で強い波が打ち寄せる海岸線を進むのは危険だ。それよりはむしろ陸路を進む選択の方が確実で安全だろう。岩泉は山深い土地ゆえ人目につかなかっただけではないのかという指摘もあるだろう。だが北上山地のど真ん中にある川井にだって伝説は豊富だ。
見落とされているだけではないのか。そう思い、岩手県立図書館に出かけ、古い新聞記事から岩泉町の義経伝説関連記事を探してみた。そして、昭和41年5月31日付けの「岩手日報」を見つけた。
見出しは「これが?弁慶の手形 岩泉の旧家で発見 経文に押して署名・朱印」。以下は記事の概要だ。
《武蔵坊弁慶のものとみられる手形が押された経文が見つかった。発見者は町内の郷土史研究家・佐々木さん。同町の神官黒田さん宅の古文書の中から偶然発見。大般若経二巻の末尾に弁慶のものとみられる手形が押されているほか、署名、朱印も。「三藤 武蔵坊弁慶 三十二歳」の署名と朱肉の押印が読みとれる。手形は普通人のものより一関節大きい。町内きっての旧家である黒田家先祖の墓碑には藤原姓が刻まれていることなどから、佐々木さんは黒田家の先祖を藤原一族と推測、その落人ではないかと推測。天台宗の山伏だったため神道を説き歩いたものとみられる》
驚きの発見である。しかし、この話が10年後の昭和51年に岩手県観光連盟によって設置された「伝説・義経北行コース」の選定にも生かされていない。当時、新たな観光コースの設定に尽力したのは義経北行伝説研究者・佐々木勝三。数々の義経伝説本を出版し、県内36カ所の立て看板選定に関わった。しかし、どうして佐々木は10年前に報道もされた弁慶の手形発見をスルーしたのか。
どんな分野にも、研究者にはそれぞれに得意とするエリアがあると聞く。逆に深く入り込めないエリアというものもあるらしい。佐々木の著書からも氏の研究エリアに濃淡があることが伺える。岩泉の伝説地はほぼ紹介されていないということは、おそらく岩泉にはブレーンが居なかったのかもしれない。
妄想スイッチをオンにして考えると、潜入してみたものの、先祖を藤原一族の落人とする岩泉の民たちの口は一様に固く、何かしら軋轢めいたものが生まれていた、とか…。あくまで妄想であるが、その流れとして触れない方がいい土地になってしまった。だとすれば、まだ眠ったままの伝承が存在する可能性があるということにもなる。もちろん伝承は脆弱。今がギリギリかもしれない。「弁慶の手形」の記事を発見したことにより、雲散霧消してしまう伝説をなんとか拾い集めておきたいという想いになっている。