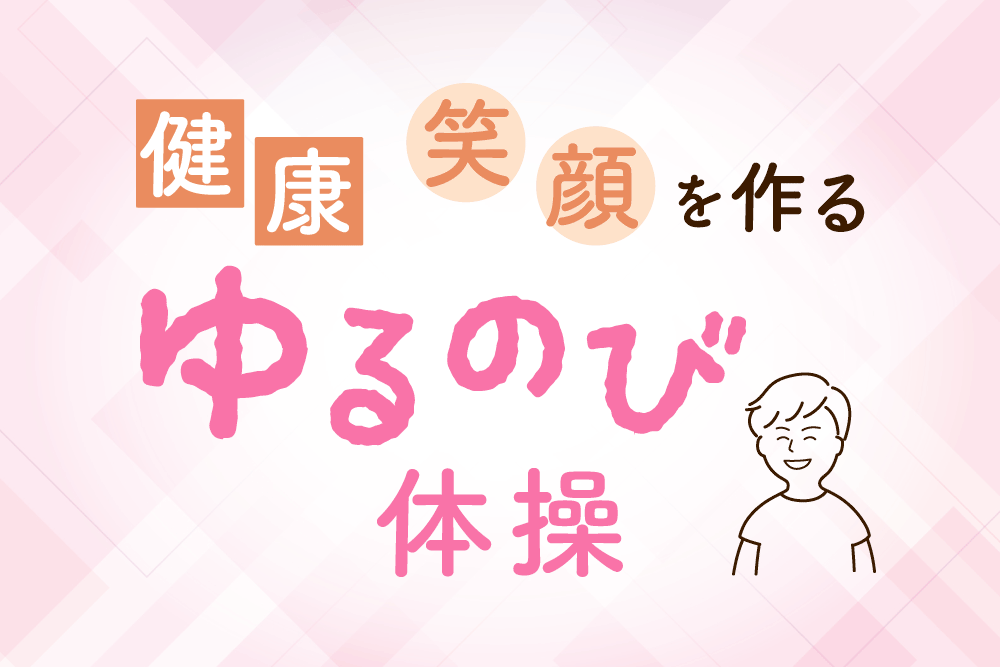超高齢化が進む現代において、肺炎は身近でありながら重症化しやすい疾患です。特に高齢者は命に関わる可能性があるため、ワクチン接種や日常の体調管理などの予防策、そして異変に気付いた際の早期受診が重要な課題となっています。今回から数回にわたり、肺炎について詳しくお伝えしていきます。
肺炎は、肺に炎症が起こる病気で、細菌やウイルスなどが原因となります。高齢の方は免疫力が低下しているため、特にかかりやすく、進行が早い場合がありますので注意が必要です。咳、痰、微熱や倦怠感、息苦しさなどの症状がみられますが、風邪やインフルエンザに似ていることもあるため、見分けが難しい場合があります。
特に、高齢者の方はこれらの症状がはっきりしないこともありますので、微熱や食欲不振など、いつもと違う様子を感じたら早めに医療機関を受診することをおすすめします。
さらに高齢者に多くみられる“誤嚥性肺炎”にも注意が必要です。食べ物や飲み物が誤って気管に入ったり、寝ている間に唾液や胃液が少しずつ気管に流れ込んだりすることで、細菌が肺に入り込み、肺炎になることがあります。そのような肺炎を誤嚥性肺炎といいます。
肺炎で亡くなる方は多く、最近の日本の死因第5位になっています。誤嚥性肺炎は死因第6位です。予防が可能ですので、日常生活の中で取り組める対策を考えてみましょう。
予防策としては次のポイントが挙げられます。
【手洗いうがいの徹底】
外出後や食事の前後に、手洗いやうがいを行いましょう。
【適度な運動】
免疫力を高めるためにウオーキングやストレッチなどを日常生活に取り入れることをおすすめします。
【栄養バランスの良い食事】
タンパク質やビタミンを多く取り、体力を保つようにしましょう。
【定期的な口腔ケア】
歯磨きや口の中を清潔に保つことで、誤嚥性肺炎のリスクが減ります。
【ワクチン接種】
肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンを接種すると、感染リスクや重症化を抑えることが期待できます。
【生活習慣病の治療】
生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満など)をしっかり治療し、動脈硬化による心筋梗塞、脳梗塞の発症を予防することで、誤嚥性肺炎が起こりにくくなります。
このような予防策を行うことで肺炎のリスクを回避することができます。なるべく多くの対策を実践してみましょう。そして体調に変化があったときは十分に注意してください。
次回以降、肺炎の原因となる細菌、治療法、ワクチンによる予防などについてお伝えします。
岩手医科大学
内科学講座呼吸器内科分野
川田 一郎
■取材協力