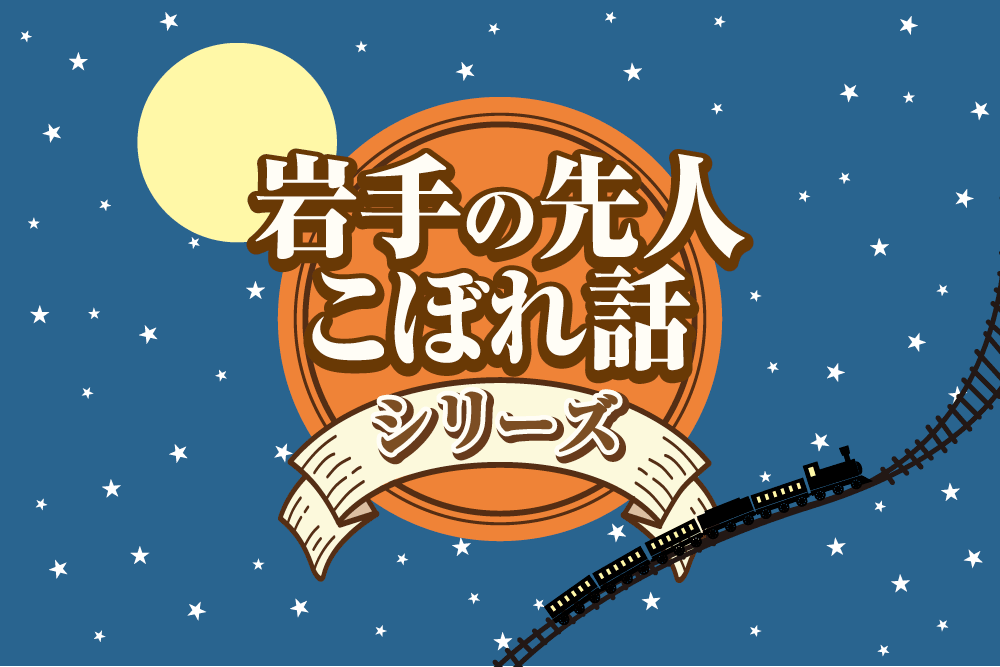毎年8月16日に明治橋付近で開催される「舟っこ流し」。炎に包まれながら舟が流れゆく、厳かな送り盆の行事です。今回は明治橋を南に渡った仙北一丁目、「旧青物町」を散策します。

良質な土壌に恵まれたこの界隈では昔からさまざまな野菜が栽培され、青物商や種物商の店が並んでいたことから「青物町」の名が付けられたと伝わります。明治橋のたもとでは、創業200年以上の「山清商店」①が今も種苗業を営んでいます。
「山清商店」の向かいにある瓦屋根と蔵作りの建物群は、創業350年以上の歴史を持ち、藩政時代から明治にかけて盛岡を代表する豪商、大地主、実業家の系譜を継承してきた徳田屋清右衛門「徳清」②の事務所と倉庫蔵とお屋敷です。現在の建物のほとんどは1887(明治20)年に建てられたもので、お屋敷の一部には解体された盛岡城の木材が使用されているそうです。社長のお母さまは、上皇后さまと聖心女子大学のご学友だったとか。学生時代の正田美智子さまが夏休みに訪れお泊まりになったといいます。
南に進むと、創業280年以上の文具店「佐々長商店」③があります。店頭の巨大な鉛筆に圧倒されながら最初の路地を右折すると、右手に見えてくるのが「金沢氏(宝田屋)邸」④です。ここは仙北尋常小学校があった場所で、当時は日本全国の学校にあった天皇皇后両陛下の写真を飾る「奉安殿」が現存していますが、一般公開はしていないようです。
さらに進み突き当たりを右折、しばらく道なりに歩くと、右手に「米徳米穀店」⑤があります。こういった町のお米屋さんもだいぶ少なくなってしまいました。その先のT字路を左へ進み東北本線下の地下道をくぐると、そこは「駒形神社」⑥です。鳥居には「東宮殿下御成婚記念」「大正13年1月26日」と記されているので、昭和天皇のご結婚を祝って建てられたものです。
地下道を戻り北進し、歩道橋を渡り明治橋へ。大正時代初期、この河原には「浮島公園」⑦という貸しボートや遊覧船のある本格的なレジャーランドがありましたが、度重なる洪水で廃園となったそうです。路地や地下道など歩いて楽しい「旧青物町界隈」、だいたい2000歩のみちくさでした。
(後編へ続く)