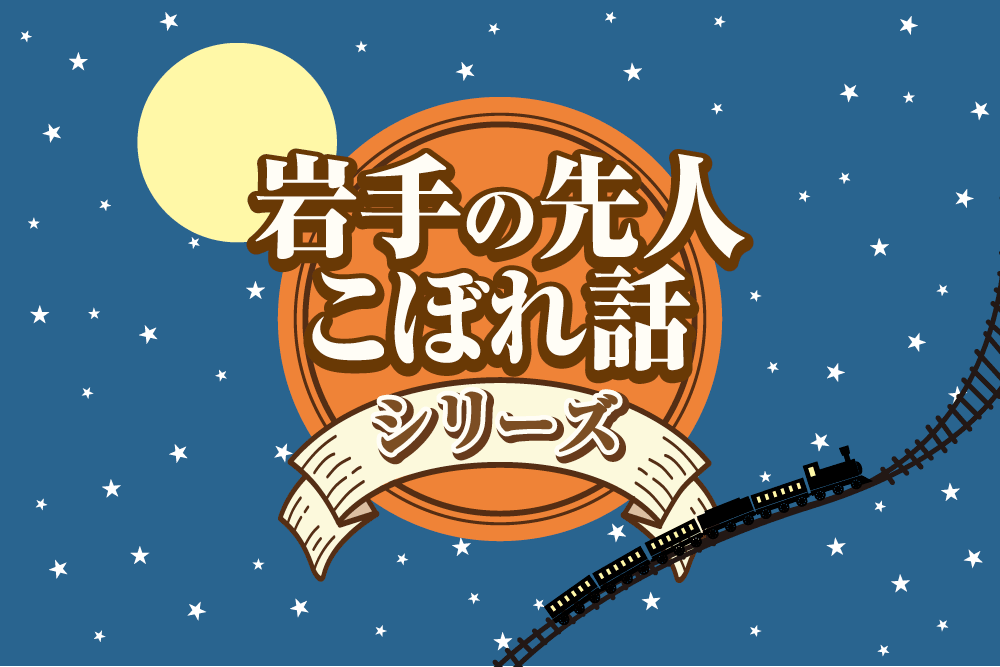狼地名は人間と狼の接点があった証しに違いない。岩手では狼を方言で呼んできたので狼地名とはいっても「おいぬ」、「おいの」と呼ぶ土地の方が多い。県北部から順に見ていこう。
まず二戸市。石切所の「狼穴(おいのあな)」は市街地中心部を流れる馬淵川の両岸にあり、狼が巣食う穴があったとは想像できない。さらに二戸には「狼久保(おいのくぼ)」が三つもある。一つは景勝地・馬仙峡の北側にある森の中。もう一つは市街地北東部・堀野には馬淵川を見下ろす山中にもあって、その背後に折爪岳の山塊がある。最後の一つは二戸と一戸の境付近、八戸道を跨ぐ形で森の中にも存在する。
次に一戸町出ル(いずる)町。浄法寺から山に入った深い森の峠付近にも「狼久保」がある。驚くことに「狼久保」は滝沢市にもある。今では国道4号と巣子の中間あたり。古くは岩手山麓の原生林だったはずのエリアだ。
雫石町には「狼森(おおいぬもり)」なる山名がある。小岩井農場「まきば園」の先、小岩井乳業の裏手に位置する山で、言うまでもなく宮沢賢治童話の舞台として知られる。雫石町長沢の葛根田川沿い、県道212号「菊の司酒造」付近には「狼沢(おいぬざわ)」がある。今や多くの車が往来する平地だが、遠い昔は岩手山麓の深い森だったのかもしれない。
盛岡市渋民には「狼峠山(おおいぬとうげやま)」という小山がある。姫神山麓の森であるが、今ではこの山腹は東北新幹線の線路で貫かれている。花巻市の「狼沢(おおかみざわ)」は東北道の花巻ジャンクション付近の町名。狼沢稲荷神社もあるが開けた農地である。花巻の東和町南成島には通称「狼洞(おいのぼら)」という集落がある。周囲に、うっそうとした森が残る低山と谷とがなだらかに続く場所。狼が棲んでいたという洞窟の伝承も残る。
「狼沢」という地名は奥州市にもある。大東と江刺田原を結ぶ国道456号の西側の山中だ。この地区の真ん中を県道197号が大田代川とともに横断する。沢筋に狼遭遇談でもあったのだろうか。奥州の胆沢平野には「上狼ヶ志田(かみおえなしだ)」、「下狼ヶ志田(しもおえなしだ)」なる地名が残るが、狼という文字が場違いなほど平坦で穏やかな気配の土地である。
対になった地名でいうと一関市花泉町には、西と東の「狼ノ沢(おいのさわ)」が並ぶ。背後に森がある平野部に近い山林にあるエリアだ。またここから少し離れた森の中にあるのが「狼沢(おおかみさわ)」。沢と言いつつ、あたりには池や沼が点在する森のようだ。
さて、今に残る狼地名の所在地からニホンオオカミの生息域の実態を想像すると、意外に人里に近く、それでいてうっそうとした森を背景にする場所に多い気がする。森の中から人里近くまでを効率的にカバーできる場所が餌取りに適し、生きていくために都合良かったのだろうか。そうした土地ゆえ、たびたび目撃されたり、ふと出会い頭に遭遇してしまうというような出来事があり、それが伝達される中で名称化され、残されたということかもしれない。
狼は人間と共存していた。だからこそ大神と称され、神々しい存在として畏怖されたのであろう。