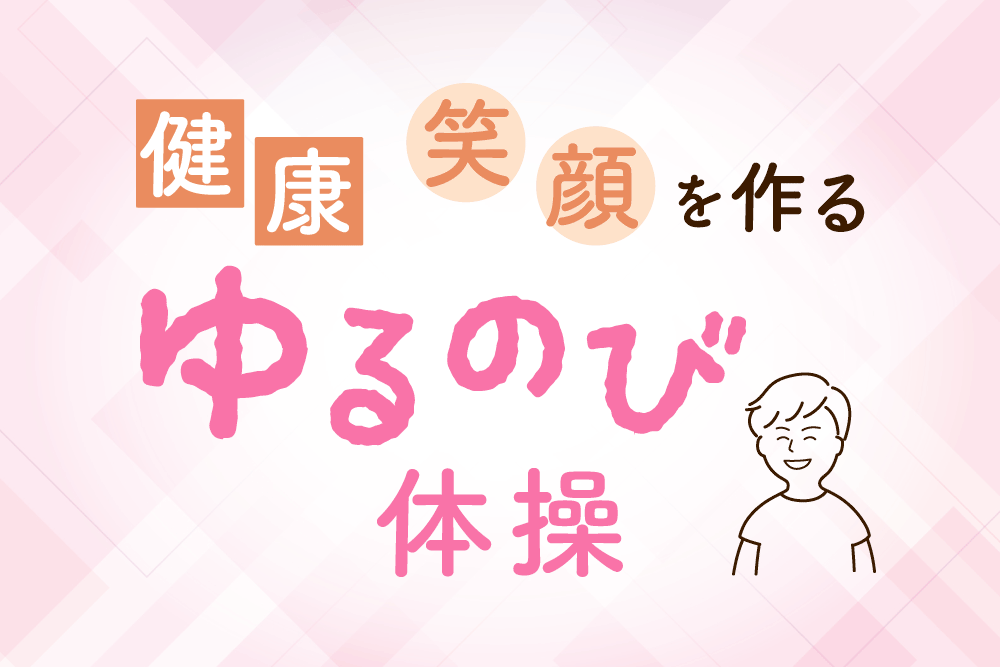早池峰山との出会いは「アケボノソウ」から始まる。数十年前のこと、小田越コースの四合目あたりで、暗紫色の花がパッと弾けるように咲いていた。鋭く星形にとがった5弁の花は、白でも黄色でもない。どちらかといえば地味な暗っぽい青紫色で、全体に青黒い斑点が散らばっていた。
刻々と変わる夜明け前の天空と消えゆく星々にたとえられた植物は、リンドウ科センブリ属のミヤマアケボノソウ。漢字で「深山曙草(みやまあけぼのそう)」と書き、花言葉は「祝福と希望」であった。
初めから草花1本1本に名があったわけではない。名付け親は全て人間である。例えば、花の美しさを愛で、香りや形・色調に魅かれたとか、採取地や薬効などの特性、発見者の名前とか茶目っ気たっぷりな珍名など、着目点は多種多様。聞いて「なるほど、さもありなん」と、その的確なネーミングに感心させられる。ちなみに、新種や新品種の約1500種以上に命名した牧野富太郎博士は1905年、早池峰で見つけた新種に「カトウハコベ」と加藤子爵の名を冠した。

早池峰は岩峰の山である。樹林帯を抜けて岩礫地に上がると視界が一気に開く。小田越を挟んで対する早池峰と薬師岳は、U字状の巨大空間を形成しており、振り向くたびに忘我の境地だ。
吹きさらしの過酷な気候風土と調和して、健気に咲く早池峰の高山植物は、国定公園特別天然記念物に指定され、1974年には標高1300m以上の連山全域に拡張された。黄色い花のナンブイヌナズナ、地表に張り付くイワウメ、固有種のヒメコザクラ・トチナイソウやハヤチネウスユキソウが育つ。しかし最近では、盗掘とシカの食害のダブルパンチで、花々が激減している。
ほらっ、花の呟きが聴こえるでしょ――連れ去らないで、早池峰で咲いていたい――。